2025年5月9日 第733号
昨年12月の一面特集「街に眠るSLに会いに行こう」では、松戸市近郊のSLが保存されている公園を紹介しました。今回はSL公園特集第二弾!ということで、東京都の公園や施設に保存されているSL達を紹介します。
1. 上千葉砂原公園(葛飾区)

交通ルールや交通道徳を学べる交通公園と、ヤギやリスザルなどを見ることができるふれあい動物園が一緒になった上千葉砂原公園にはD51型502号機が保存されています。D51型は全国的に多数保存されている、日本で最も製造された蒸気機関車です。現役時代は主に貨物列車を牽引していました。
上千葉砂原公園に保存されている502号機は昭和16年に製造され、昭和47年に廃車されるまで、広島県や新潟県などで活躍しました。走行距離は地球約46周分です。廃車後、交通機関の近代化と科学の進歩を知る歴史的な教育上の資料として、同公園への設置が決まり、現在まで保存されています。
アクセスはJR常磐線亀有駅から京成タウンバスに乗車し、上千葉砂原公園バス停で下車すぐです。SLのそばには桜の木が植えてあるので、春には桜とSLの並びを見ることができます。


2. 入新井西公園(大田区)

京浜東北線大森駅から徒歩5分ほどの場所にある入新井西公園にはC57型66号機が保存されています。C57型は日本全国で急行列車などの旅客列車の牽引機として活躍し、現在でも1号機がSLやまぐち号やSLスチーム号の牽引をしています。
入新井西公園に保存されている66号機は昭和13年に製造され、主に九州地方で活躍し、昭和48年に廃車されるまで、地球約79周分を走行しました。なんと、現在の京都鉄道博物館の敷地に存在した、梅小路機関区に配備されたこともあったそうです。旧梅小路機関区の扇形車庫は、現在も京都鉄道博物館の一部として残されており、多くのSLを展示しています。記者は京都鉄道博物館が大好きなので、旧梅小路機関区の扇形車庫を拠点として活躍していた時代を想像し、心が躍りました。
入新井西公園のSLは12時、15時の毎日二回、動輪が5分間稼働し、同時に汽笛を聞くことができます。稼働する動輪や鳴り響く汽笛から現役時代の活躍を想像することができますね。



3. 城北交通公園(板橋区)



都営三田線蓮根駅から徒歩5分ほどの場所にある城北交通公園には2種類のSLが保存されています。
まずは、上千葉砂原公園などの多くの場所で展示されている、最も製造されたSLでおなじみのD51型です。城北交通公園には513号機が保存されています。このSLは主に新潟県や山形県で昭和47年まで活躍しました。SLの近くには踏切や腕木式信号機、都バス、交通資料館などがあります。交通資料館の中には、蒸気機関車の模型や昔の列車の写真、Nゲージの模型電車などを展示しており、小規模ながら鉄道好きには楽しめる場所となっています。
次に、長さはわずか4・7メートルの小さなSL、ベビーロコ号です。明治45年にドイツで製造されたSLで、和歌山県の有田鉄道(鉄道事業は平成15年年廃止)で使用され、紀州の山野で活躍しました。戦後、東武鉄道がガソリン機関車と交換で取得したものの、小さい機関車で多くの貨車を引けなかったため、長らく放置され、昭和33年7月以降は東武東上線のときわ台駅で展示されていました。最高速度は時速20キロメートル、性能は牽引力10車両程度です。とてもかわいらしいSLですね。

4. 芝浦工業大学附属中学高等学校(江東区)
ゆりかもめ新豊洲駅下車すぐの芝浦工業大学附属中学高等学校には、403号蒸気機関車が保存されています。403号蒸気機関車は、明治19年にイギリスのナスミス・ウィルソン社で製造され、日本国有鉄道の前進の内閣鉄道局が輸入しました。大正3年に現在の西武鉄道国分寺線、新宿線の一部にあたる川越鉄道に譲渡され、約40年間活躍しました。その後、上武鉄道(昭和61年廃止)に譲渡され、昭和40年に廃車、廃車後はユネスコ村や西武鉄道横瀬車両基地で静態保存されていましたが、令和4年、芝浦工業大学附属中学高等学校100周年記念事業の一環として、同校への保存が決まり、移設されました。この際に、失われていた製造銘板とナンバープレートの復元・取付を行うなど、徹底した補修整備を実施し、現在の美しい姿に蘇っています。
この403号蒸気機関車は、毎日12時と17時に汽笛音がなります。なんと、この汽笛音と走行音は、博物館明治村で動態保存されている蒸気機関車9号から録音されたものだそうです。SLが大好きな記者は、この音源である蒸気機関車9号に会いに博物館明治村へ行ってみたくなりました。
また、403号機関車の近くには、明治5年に新橋~横浜間が開業する際に造られた、海側の高輪築堤の築石も展示されています。この石は品川車両基地の再編や高輪ゲートウェイ駅の新駅を伴った大規模開発の中で令和2年に発掘されました。高輪築堤は発見後、埋め戻されてしまったため、本物の築石の一部を見ることができて嬉しかったです。



今回紹介したSLは、すべて運転席に入ることができ、昭和時代に製造されたものだけでなく、明治時代に製造されたSLも見学することができました。そのため、製造された時代や用途の違いによって、車体の大きさや運転席の機器類にさまざまな違いがあることを、実際に見て体感することができました。一両一両異なるSLをアナログな計器を見ながら運転していた昔の運転士さんはとても凄いですね。
(ベース)






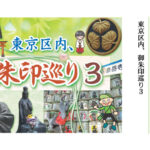





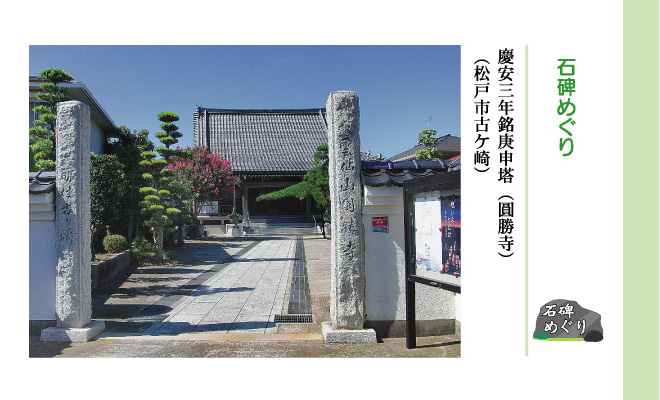




この記事へのコメントはありません。