2025年4月4日 第731号
相模台は、かつて武士の城が築かれた歴史を持ち、戦国時代には要衝として機能していました。その後、時代の変遷とともに武士の影は薄れ、教育の場として発展を遂げます。近代に入ると、学校や学習施設が整備され、多くの学生が集う地域へと変貌しました。現在では、歴史的な名残を残しつつも、学びの場としての役割を担っています。相模台の風景は、武士の時代から教育の地へと移り変わった歴史の証人として、人々に語り継がれています。
鎌倉時代、北条長時が城をはじめて築く
鎌倉幕府の絶対的な存在であった源頼朝が急死した後、御家人の中で勢力を拡大していったのが北条氏です。最終的には、将軍を補佐して政治を執る体制を確立しました。
しかし、有力な御家人を完全に排除するには至らず、合計十三人による合議制による政治が展開されました。結果として、この合議制により平和な時代が続きます。
この合議制を始めた北条泰時が没すると、幕府内では再び権力闘争が表面化し、宝治合戦や霜月騒動などの事件が発生。これらをきっかけにして、北条氏本家の権力が強大化していきました。
北条氏本家による専制体制が決定的になったのは、建長の政変のときです。有力御家人の謀反計画が発覚し、次々に処罰されたことで、九条頼嗣将軍は廃されました。代わりに宗尊親王が擁立され、将軍は祭司や儀礼を担う象徴的な存在へと変わりました。
このとき、北条氏本家の時頼は、幼い時宗に家督を譲り、若くして出家する道を選びます。これは家督争いを避けるためとされていますが、その際に中継ぎとして執権職を託されたのが、分家の北条長時でした。
この北条長時が、相模台に初めて城を築いたと伝えられています。執権職に就く数年前のことでした。
北条相模守高時が居城したことから「相模台」と呼ばれるようになる

当時、房総三国の守護職であった北条長時が築いた城がどの程度の規模であったのかは、遺構がほとんど残っていないため不明です。また、岩瀬城が存在したとされることから、これが後に相模台城と呼ばれるようになったのか、あるいは長時が築いたのが岩瀬城で、相模台城は戦国時代に高城氏が築いた可能性も指摘されています。
ただし、相模台地に城が存在したことは確かなようで、鎌倉時代末期に病を理由に執権職を退いた北条氏本家の北条相模守高時がその城に住んでいたとされています。これに由来し、「相模台」と呼ばれるようになったと伝えられています。

第一次国府台合戦(相模大合戦)の舞台となる

相模台とその周辺は、戦国時代に合戦の舞台となりました。「第一次国府台合戦」と呼ばれる戦いですが、実際には相模台上で緒戦が行われ、主戦場は相模台の眼下に広がる現在の松戸駅周辺だったとされています。
この合戦は、関東足利氏の正当性をめぐる争いでした。足利晴氏の命を受け、足利義明討伐に向かった北条氏綱らと、義明に従う里見氏らが激しく戦いました。
相模台城には足利義明軍の先鋒隊が在陣し、江戸城を発して向かってくる北条軍の動静をうかがっていたようです。しかし、北条軍が松戸方面で江戸川を渡り、相模台へ来襲することまでは予想していなかったと考えられます。その結果、かつて松渡城があった台地(現在の戸定邸)への北条軍の布陣を許してしまいました。
こうして、目と鼻の先で睨み合う形となった両軍は、相模台周辺で激突することになります。
双方の戦力は拮抗していましたが、足利義明に加勢していた里見軍の戦意はあまり高くなかったようです。また、義明は個人戦の要素を重視する傾向があったとされ、それも影響して敵中に深く入り込みすぎ、孤立して討ち死にしてしまいます。これにより、第一次国府台合戦の勝敗が決しました。


明治から大正の時代には、松戸競馬場として賑わう(中山競馬場の前身)
明治時代の終わりごろ、軍馬の改良を目的とした競馬場の開設が全国各地で相次ぎました。相模台もその一つとして選ばれ、馬場として設計・整備され、松戸競馬場が誕生します。
松戸競馬は開催直後から盛況を博しましたが、馬券による賭博が世論の批判を受け、馬券販売が法律で禁止されました。その結果、競馬場は見物料のみでの運営を余儀なくされ、大正時代の初めには経営が立ち行かなくなってしまいました。
賭け事である競馬が批判され、陸軍に売却される
その松戸競馬場の土地を買い取ったのは、工兵学校の敷地を探していた陸軍でした。
その後、陸軍工兵学校が相模台に開校されます。開校当初は仮設の建物しかありませんでしたが、数年かけて整備が進められ、大正時代の中頃に完成しました。現在、松戸中央公園には当時の正門門柱や歩哨舎が残されています。
相模台が工兵学校の地として選ばれた理由は、教育総監部工兵幹部直属であるため、東京に近いことが望ましかったためです。また、野戦や坑道、重架橋の演習に適した地形が、当時の松戸町周辺に広がっていたことも要因の一つでした。

陸軍工兵学校が開校し、地形を活用した演習や訓練を経た工兵たちが、各地の連隊へと配属される
陸軍工兵学校の教育課程では、築城訓練に和名ケ谷や八柱の練兵場が、架橋演習には江戸川が利用されました。また、京成松戸線(新京成線)は鉄道敷設の訓練線として活用されていたようです。このような教育機関は全国で松戸にしかなく、当時は「工兵のまち松戸」とも呼ばれていました。
なお、相模台にある「地獄坂」は、厳しい演習で疲労困憊した工兵学校の生徒たちが登るのに苦労したことから名付けられたとされています。
陸軍工兵学校を卒業した者は、部隊の中核を担う下士官となり、全国各地の連隊へと配属されました。当時の軍国主義的な風潮の中で、職業軍人として尊敬されていた下士官は、ときには分隊や小隊を指揮することもあったようです。


太平洋戦争終結後、東京芝浦の工業専門学校が入り、千葉大学工芸学部を経て、聖徳学園や市営公園など現在の姿へ
太平洋戦争が終結すると、陸軍工兵学校は当然ながら閉鎖されました。その空いた校舎に入ったのが東京芝浦の工業専門学校で、昭和時代の新制大学発足に伴い、千葉大学工芸学部となりました。
その後、同学部は工学部へと改称され、昭和時代の中頃に西千葉へ移転します。ただし、付属の天然色工学研究施設は相模台に残されました。しかし、翌年に火災が発生したことで、当時まで使用されていた陸軍工兵学校の建物はすべて取り壊されることとなります。
その後、整地された相模台地は、聖徳学園や松戸中央公園、松戸市立第一中学校などに分けられました。平成時代に入ると、聖徳学園には四年制大学も併設されました。
この聖徳大学の構内には二基の円墳が残されています。これらは、第一次国府台合戦で戦死した足利義純らを葬ったものともいわれています。ただし、もともとは校舎裏に円形の塚が一基のみ存在しており、陸軍工兵学校による復元の際に二基となったようです。相模台城跡の周辺には、かつて同様の塚が大小いくつもあったと伝えられています。それらからは土器片などが出土したとされ、もともとは古墳群の一部だったと考えられています。(かつ)


■参考図書/「歴史街道」「国府台合戦を点検する」「図説 戦国里見氏」「東葛の中世城郭」「新京成電鉄沿線ガイド」「松戸史談」「わがまちブック 松戸」「東葛流山研究」「国府台の合戦」




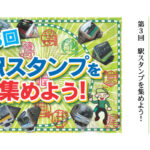
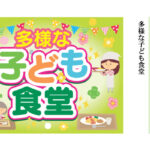



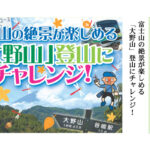



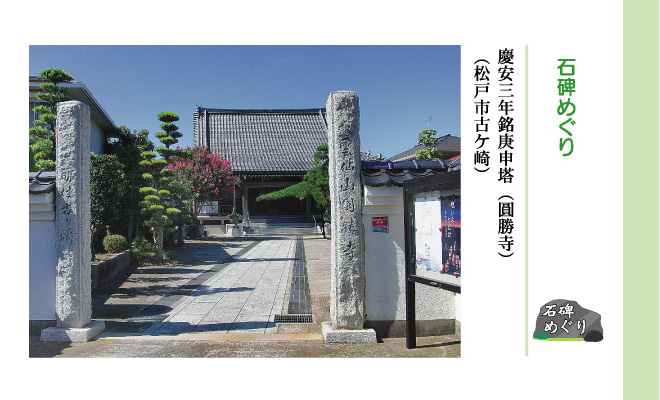




この記事へのコメントはありません。