2025年11月7日 第745号
一遍上人は「踊り念仏」で知られる時宗の開祖です。松戸市上本郷にある本福寺は、松戸市内で唯一の時宗寺院です。一遍上人の最初の弟子である、二祖・他阿真教上人が開いた寺で、一遍ゆかりの地としてその信仰を今に伝えています。
本福寺で見られる一遍上人の銅像
松戸市内唯一の時宗寺院であり、一遍上人の銅像のある本福寺の前には「吉田松陰脱藩の道」の碑が建てられています。黒船来航の衝撃に揺れる幕末、長州藩邸を脱走した吉田松陰は、海外渡航を目指す無謀な旅に踏み出しました。禁制を破ってまでも志を貫こうとしたその行動は、常識からすれば狂気にも映ります。その夜、松陰が身を休めたのが下総松戸の本福寺でした。
時宗の開祖・一遍上人は、定まった住処を持たず、「一所不住」を掲げて全国を遊行し、踊り念仏をもって庶民に救いを説きました。安住を拒み、ただ念仏と共に漂泊する姿は、秩序や権威に抗して「生の真実」を求め続ける在り方そのものでした。
松陰が松戸の本福寺に一泊したことは、単なる地理的偶然と見ることもできます。しかし一方で、その選択は象徴的でもあります。幕府の制約を破り、世界へと飛び出そうとする志士が、一遍ゆかりの「漂泊の宗」の寺に身を休めたその一夜は、志と漂泊が交錯する瞬間だったのかもしれません。
本福寺の境内に入ると、左手の釣り鐘の隣に、一遍上人の銅像を仰ぎ見ることができます。


一遍上人ではなく、二祖の他阿真教(たあしんきょう)上人が開基した理由
一遍上人自身は、特定の宗派を開く意志はありませんでした。彼は自らを「無戒無道」と称し、特定の教義や組織に縛られることを拒みました。彼の思想は、ひたすら念仏を唱え、誰でも救われるという「他力」の精神にありました。
彼の集団は、念仏を唱えながら全国を遊行(ゆぎょう)する人々、すなわち「時衆(じしゅう)」と呼ばれていました。これは特定の宗派名ではなく、その活動様式を示す呼称でした。
「時宗」という宗派名が確立されたのは、一遍の死後、彼の弟子である他阿真教上人らの時代になってからです。彼らが教団としての体裁を整え、一遍の教えを継承していく中で、後世になって「時宗」という呼び方が定着しました。
鎌倉時代後期、他阿上人が柏市布施を遊行したのを契機に同地に善照寺が創建され、翌年には松戸で本福寺が開かれました。本福寺には、そのことを裏付ける「鉦鼓(しょうこ)」と呼ばれる円形青銅製の鉦(かね)が残されています。檀家の屋根裏から発見されたもので、「嘉元改元癸卯天九月日、本福寺開祖他阿弥陀佛」と銘があり、日本で六番目に古い鉦とされます。
一遍上人は「一処不住(いっしょふじゅう)」を主義として全国を遊行(ゆぎょう)した

一遍上人は、生涯を「漂泊の聖者」として歩み続けました。彼が掲げた「一処不住(いっしょふじゅう)」とは、どこにも定住せず、常に新しい地へと遊行を続ける姿勢を意味します。財産も家も持たず、弟子たちとともに道を歩み、出会う人々にただ念仏を唱えることを勧めていきました。
その根底にあったのは「捨ての思想」です。身分や財産への執着を捨て、組織や権威へのこだわりを捨て、ひたすらに一人ひとりの救済に心を注ぎました。当時、仏教諸派は寺院や荘園を背景に力を増し、時に政治や経済と深く結びついていました。しかし一遍は、そうした権力の網に自らを絡めることを拒みました。彼の関心は、組織を広げることではなく、名もなき庶民が「念仏ひとつで救われる」という実感にありました。
旅の途上では「賦算」と呼ばれる念仏札を配り、誰でも救いにあずかれることを示しました。
一遍は宗派を築くことなく世を去りますが、その教えを整理し、教団を整えたのは弟子の他阿真教でした。

河野水軍の一族に生まれ、十歳で母を亡くし、十三歳で出家する
一遍上人の烈しい生涯は、「漂泊と捨て」に象徴されます。その思想と行動の源流をたどると、彼の生まれ育った環境に深く根ざしていることがうかがえます。
一遍は伊予国に勢力を持っていた河野水軍の一族に生まれました。しかし、その二十年ほど前に、鎌倉幕府と朝廷の間で承久の乱が勃発し、この戦いで敗北した朝廷方(後鳥羽上皇側)にいた河野氏は幕府から所領を没収されるなど、大きな打撃を受けました。没収された所領の一部は後に返還されましたが、これにより一族内部で家督を巡る争いが激化し、不安定な状態が続きました。一遍上人(当時は河野通秀)は、こうした一族の没落と混乱の中で育ちました。彼は若くして出家しましたが、その背景には、武士社会の無常観や権力争いに対する失望があったのではないかと考えられています。
十歳のときに母を亡くし、さらにその二年後、父が出家して入道すると、一遍もまた十三歳で仏門に入ります。まだ少年でありながら、武士の道ではなく僧侶としての道を歩み始めたのは、母を失った喪失感を抱えて生きるなかで「救い」を求めた自然な流れであったとも言えるでしょう。
いったん還俗した後、再出家して、いっさいを捨離する念仏称名ひとすじの生活に入る

一遍上人の生涯は、常に「捨て」と「漂泊」に貫かれていますが、その過程には大きな転機がありました。父の死をきっかけに一遍は故郷へと戻り、そこで一時、出家の身を離れ、在家として暮らしていたと伝えられています。出家したまま妻を娶り、家庭を持ちながら生活していたとも言われています。
それは、在俗の人々と同じように日々を送り、家族と共に安らぎを求める日常であったかもしれません。しかし、一遍の心の奥底には、無常の真理に揺さぶられる思索が続いていたのでしょう。やがて彼は「人は身(行為)・口(ことば)・意(こころ)の三業によって流転輪廻を繰り返す」という真理を深く悟るに至ります。人間が営むあらゆる行いは、知らぬ間に業を積み重ね、再び生死の苦しみに縛りつける――その厳しい認識が、一遍の心を突き動かしました。
そして、一遍は決断します。自分自身が新たな業をつくり出すことを徹底的に止め、すべてを捨ててただ念仏称名にひとすじに生きると。こうして彼は再び出家し、以後は家も財も、世俗的なつながりも手放し、ただ漂泊の旅に身を置いていきました。


「踊り念仏」は、言葉や文字に依らず、体全体で念仏の喜びを表現するものだった
一遍上人が広めた「踊り念仏」は、時宗を象徴する実践としてよく知られています。念仏というと、口に称えるもの、あるいは経文を唱えるものという印象が強くありますが、一遍の念仏はそれにとどまりませんでした。彼が示したのは、言葉や文字に依らず、体全体をもって念仏の喜びを表現する独自の形だったのです。
踊り念仏では、人々が円を描くように集まり、声を合わせて「南無阿弥陀仏」と唱えながら、足を踏み鳴らし、手を打ち鳴らし、全身を使って念仏を表します。そこには形式や作法の堅苦しさはなく、ただひたすら阿弥陀仏への信頼と救いの歓喜があふれています。この姿は、身分や立場を超えて誰もが参加できる開放的な場を生み出しました。
鎌倉時代は、戦乱や飢饉、疫病などによって人々が不安に苛まれていた時代でした。そうした社会にあって、一遍の踊り念仏は、苦しみの中でも救われるという確信を与え、人々の心を解き放つ役割を果たしました。声を合わせ、体を動かすことで得られる一体感は、念仏の教えを理屈ではなく、身体の奥深くに刻み込むものであったといえます。 (かつ)
■参考図書/
「新京成電鉄沿線ガイド」「東葛流山研究」「歴史人」「名僧列伝」














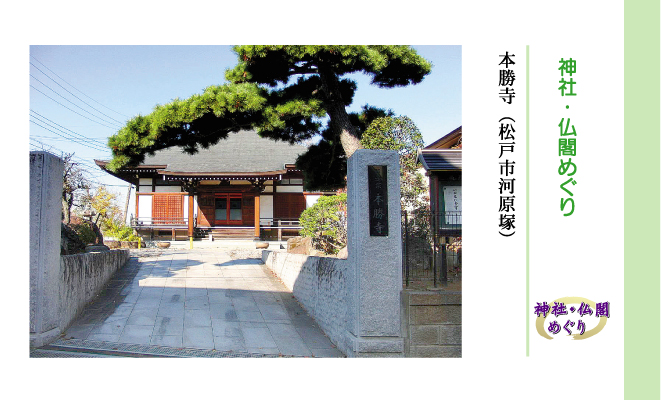



この記事へのコメントはありません。