二十六夜塔(松戸市小金原)
2025年7月4号 第737号
平安中期の『延喜式』に載る「式内社」か、との説もある茂侶神社(本紙720号で、かつ記者も言及)の、鳥居のすぐ外に建っています。庚申塔や仏教系碑群が集められた中の一つ、「月待ち」に関わる碑です。
昔の暦では新月の日がついたち。十五日がだいたい満月で、十五夜お月さん。その何日も後の二十六夜の月は、未明に東から昇る、三日月が左右反転した細い円弧状です。この月の出を、旧暦7月などに江戸時代の人々は集まり、待ちました。愛染明王にまつわる信仰で、月光から阿弥陀・観音・勢至の三尊が現れると言い伝えられていました。
この「二十六夜待」が都市部でいつしか、夜通し飲食や遊興に耽る一大行事に変質。江戸の高輪では、屋台ひしめく中、タコの被り物のコスプレおじさんまで闊歩……と賑やかな、歌川広重の浮世絵が残っています。でもそんな楽しみも、規律を厳しく引き締めた天保の改革(1841年~1843年)で廃れたのだとか。
松戸では、同種の民間習俗に関連する二十三夜塔はぽつぽつ見られますが、二十六夜塔はここだけなのだそう。天保の改革直後の、1844年建立なのも珍しく、新たな謎が浮かびます。小金原の月待ちって、江戸と違って改革の縛りから脱した、穏やかなしっとり系イベント?それとも改革が頓挫するや、ここを先途と碑を造り、二十六夜を派手に寿ぎ騒いだのでしょうか?(さっくん)
◎所在地/松戸市小金原5ー28ー13









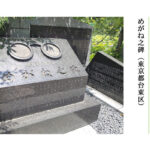

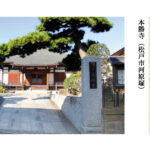


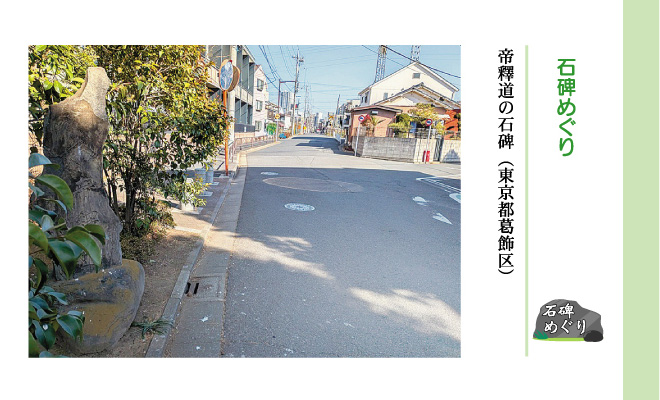




この記事へのコメントはありません。